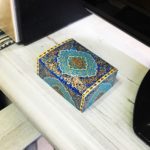好きな人に好きだと言われない運命でも生きようと思った。

好きな人に好きと言われない運命!ゲイのぼくは日常生活で普通の恋愛ができないことを悟った
・ゲイとノンケは決して結ばれることのない運命
・ぼくは彼に好きだと言ってもらうのが夢だった
・ゲイのぼくは日常生活の中で普通の恋愛をすることができない
・ゲイのぼくは好きな人に好きだと言われない運命でも生きようと思った
・「超越の愛」
目次
・ゲイとノンケは決して結ばれることのない運命

ぼくが初めて人を好きになったのは高校2年生だった。好きになった相手は同級生の、同じクラスの男の子だった。彼はもちろん女の子が好きだった。彼がぼくを好きになってくれる可能性は0に等しかった。彼は教室でぼくを膝に乗せてくれたり、「可愛い」って言ってくれたり、帰りのバスの中で2人切りになった時には膝枕してくれて髪を撫でてくれたりして、ぼくは自然と彼のことを好きになっていった。
例えばぼくが女の子だったなら、そんな関係性だともはや恋愛に発展していると見なされるだろう。だけどぼくは男だった。どんなに愛されているような素振りを見せられても、それは彼がぼくを好きだということを意味することは決してなかった。ぼくと彼はなんだか恋人みたいだったけれど、ぼくと彼が両方男で、彼が女の子を好きである限り、ぼくたちは決して恋人にはなれなかった。
・ぼくは彼に好きだと言ってもらうのが夢だった

ぼくは彼に好きだと言ってもらうのが夢だった。夢というか、とても自然とぼくを好きになってくれるように祈っていた。「祈って」いたのは、絶対に好きになってもらえないことをわかっていたからだ。祈るくらいしかできることがなかった。ぼくは男の肉体を持っていて、彼は女の肉体を本能のまま必死に求めている。ぼくと彼の心が通い合い、彼がぼくに好きだと言ってくれる見込みはなかった。絶対に叶わない夢を、ぼくは切実に見ていた。
ぼくは好きな思いが我慢できなくて、ノンケの彼に2回「好き」だと伝えてみた。もちろんぼくの夢は叶うことがなかった。彼がぼくを好きだと言ってくれることはなかった。いつもはぐらかされたり、ぼくが好きだと伝えたせいで距離ができたりしてしまった。ぼくは好きな人に、好きだと言われない人生を歩むのだと悟った。これから先また日常の中で恋をしても、普通の人々みたいに好きだという気持ちを返され心を通い合わせることは決してないのだと虚無感に襲われた。
・ゲイのぼくは日常生活の中で普通の恋愛をすることができない

周りの友達が羨ましかった。もしも普通の男女が「可愛い」と言って髪を撫でていたり、膝枕して甘えていたりすればそれはもはや明らかな恋愛模様であり、「好きだ」と言い合っていても何の違和感もないだろう。だけどぼくの場合は好きな人とそんな関係になっていたとしても、決して「好きだ」と言われたり、付き合ったり、結婚したり、子供を作ったりできない運命なのだと気がついた。
テレビや小説の中にあるみたいに、日常生活で普通に人を好きになって、お互いに心惹かれ合って、告白して、付き合って、幸せになって、そんな当たり前の世界が自分の生命には内蔵されてないことが悔しかった。そのような世界が展開されないのならぼくはどうやって歩みを進めればいいのか、見当もつかずに未来に絶望した。
インターネット上で男の肉体を求める男性と交流を深めることは可能だろう。だけどそれは高校生のぼくが思い描いていた世界ではなかった。ぼくが当たり前のように人生で通り過ぎると思っていた世界は、日常生活の中で誰かを好きになって、告白して、付き合って、結婚して、幸せになるということだった。きっと多くの人々にとってそれが当たり前の世界として、心の片隅に存在していることだろう。だけどぼくはそんな世界へ参加することを許されていなかった。ぼくは夢のような「普通の国」への入場券を持っていなかった。入口の前で、それまでは当然のように入れると信じていた「普通の国」から入場拒否されて、立ち尽くして取りつく島もなかった。
・ゲイのぼくは好きな人に好きだと言われない運命でも生きようと思った

難しいことなんか決して望んでいない、当たり前のことしか望んでいない、誰もに与えられるものを、ぼくにも与えてほしいと願っただけだったのに、神様はぼくにとってそれは贅沢だと、ぼくに「普通の国」をよこさなかった。ぼくはどうやって生きていけばいいのだろう。誰に相談することもできず、彼を好きな気持ちに押しつぶされそうになりながら、ただただ孤独を深めていった。
日常生活の中で自然とできた好きな人に、好きだと言われることは一生ないんだと考えながら、高校生のぼくは毎日お風呂で泣いていた。ひとりきりになれる場所がお風呂しかなかったからだった。好きな人に好きと言われるためには、とんでもない超越が必要だった。すなわちぼくが日常生活の中で男の子を好きになっても、その男の子は当然女性の肉体が好きだろうから、女性を好きだという野生的で原始的で絶対的な本能を超越し、ぼくを好きだと言ってもらうしかなかった。
そんな超越がこの世に存在するはずがない、ぼくは本当に好きな人には好きと言われないまま一生を終えるんだ。そんな風に思うと生きる意味を見失っていた。どうしてぼくの願いが叶うためには、絶対に困難な「超越」が必要なのだろう。ぼくは自分の背負っている運命の理不尽さと奇妙さに、激しい風の吹きすさぶ荒野の中でひとり立ちすくんでいる思いがした。ぼくには「超越」が必要だ。与えられるはずもない「超越」が必要だ。はるかなる、手の届かない「超越」を夢見ながら、ぼくは神様が気まぐれに「超越」をもたらすことだけを願った。自分の力ではどうしようもない。何ひとつぼくにできることはない。絶望の中、ただ与えられることだけを願った。
・「超越の愛」
・ぼくの高校時代の初恋について
・ぼくの大学時代の恋愛について
・同性愛に関する記事一覧はこちら!