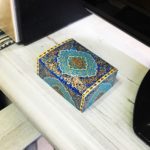成績学年トップだったぼくがノンケの同級生を好きになって大学受験に大失敗した話
・ぼくの初恋は高校2年生だった
・ぼくが成績学年トップだった理由
・ぼくは好きな人を見ることがつらくて学校に行けなくなった
・ぼくは大学受験を失敗した
・他人の悲しみを知らずに他人を裁くことはできない
・ぼくの初恋は高校2年生だった

高校2年生の時、ぼくは同級生の男の子に恋をした。それがぼくの初恋だった。相手はもちろん異性愛者(ノンケ)で、ぼくは叶わない思いを抱きながら残りの高校生活を送らなければならなくなった。人を好きになることは素晴らしいことで、恋愛は楽しいものだというイメージをなんとなく持っていたけれど、実際に自分が人を好きになって、それが男から男への思いだと苦しくて悲しいことの連続だった。
髪を撫でてもらったり、「かわいい」って言ってくれたり、二人きりのバスの中で秘密で膝枕してもらったり、最初は楽しい思い出も多かったけれど、結局はどうしたって叶わない思いを抱いているのだと知る度に、ぼくの心は深い霧がかかったみたいに前が見えなくなった。ぼくが人を好きになっても絶対に思いは届かないんだ、今だけじゃなくてこれからもずっと、人を好きになる度にこんな風に叶わない切ない思いを抱えながら一生生きていかなければならないのだと、高校生のぼくは既に未来に絶望していた。
・ぼくが成績学年トップだった理由

中高一貫の学校に通っていたぼくは、中学1年生の頃からずっと成績学年トップを維持していた。周囲からは賞賛され、本来ならばいい大学に入って、いい会社に就職して、いい暮らしを送りながら、いい家庭を築くということを夢見られただろう。けれど初恋を経験したぼくにとって、そんな未来予想図は何の意味も持たなかった。ぼくは何に優れていようと、何に秀でていようと、どうせ一般的な幸せなんか掴めないことを予感していた。それならばいっそ、何の才能も持たない方がよかった。ぼくは何もかもを喪失して、何者でもない者になりたかった。
自分自身でもなぜ学年トップなのかわからなかった。宿題ならばきちんと真面目にこなしていたけれど、試験勉強だって家にあったドラえもんのビデオを見ながらやったりして、特別真面目な態度を維持していたわけではなかった。今ふり返ってみれば、ぼくが学年トップということに揺るぎない肯定を感じていたのかもしれない。それは自分が「男を好きになる男」だという、徹底的な否定の雨から自分自身を守るための、最も重要な傘だったのかもしれない。
ぼくの生命には徹底的な否定が一生に渡り降り注ぐのだということが運命として決められていたから、ぼくが徹底的な否定に押しつぶされてこの世から消えてしまわないように、神様が揺るぎない社会的肯定を才能として与えてくれたのかもしれない。
・ぼくは好きな人を見ることがつらくて学校に行けなくなった

そんな風に周囲から見れば「優等生」だったのかもしれないけれど、ぼくは他人の裁きなんてどうでも良かった。それよりもただ、自分の中にいつまでも生じ続ける叶わないと運命付けられた好きな思いにどう対応すればいいか迷うことで精一杯だった。高校生のぼくは自分の悲劇的な初恋に対応しきれず、「優等生」だったにもかかわらずたまに無断で学校を休み始めた。同じ教室にいる大好きな彼のことを見るだけでも、胸が苦しくて耐えられなくなった。彼を見ているだけでも、自分自身の未来や幸せが否定されていくような感覚を覚え始めていた。
彼と同じクラスだった高校2年と3年は、大学受験として最も重要な時期だったけれど、ぼくにとっては大学受験なんかよりも、心の中に巻き起こる感情の嵐を制御することで精一杯だった。どうせ幸せになれないのに大学受験に成功しても意味なんてないと、初恋を経験した高校生のぼくはぼんやり感じていた。
ある日担任の先生が教室の前で「大学受験に失敗する人の特徴」というのを読み上げて、その中のひとつに「叶わない恋をしている」という項目があって教室中が明るい爆笑に包まれていた。沸き起こる見ず知らずの笑いの中で叶わない恋をしているぼくだけが、心の中で泣きたい思いを必死にこらえていた。
・ぼくは大学受験を失敗した

高校2年と3年の間に、彼とは仲良くなったり喧嘩したりを繰り返しながら、結局卒業も間近に迫った最後にはまた仲良くなって、一緒に勉強したり学校から帰ったり、そんな日々を尊く感じていた。高校を卒業すれば、もう彼とは会うこともなくなるだろう。ぼくは嵐のようなこの初恋からやっと解放される嬉しさと安堵、そして大好きな人と会えなくなる少しのさみしさを噛み締めていた。ひとつだけ同じ大学を2人で一緒に受けに行ったけれど、きっとそこに行くことはないだろう。試験の帰りの電車の中で、甘えさせてくれたことだけが嬉しかったことを覚えている。
高校を卒業して本命の国立医学部を受ける少し前から、彼からのメールの返信が来なくなってぼくの心はまた愚かしく乱れていった。それでもいつもなら試験の時だけは集中できたけれど、不幸なことに国立大学入試の朝から食あたりを起こして、発熱や嘔吐を繰り返してしまった。それでもなんとか解熱剤を飲んで、食べると吐いてしまうからバナナだけを食べて試験に臨んだけれど、結局は落ちて失敗してしまった。
だけど当時のぼくは入試のことなんてどうでもいいと心から思っていた。それよりも自分の心を支配している野生的な激しい恋の感情と、どうしようもなく思いが叶わないという運命から、高校を卒業して彼と会わなくなることによって一時的にでも逃れられることを心から願っていた。もう心の中の嵐にふりまわされない世界へと帰りたい。
結局それから二度と彼からメールが返ってくることはなかった。理由はわからなかったけれど、もはや関わらなくなるというのならそれが自分にとっても、彼にとっても一番いい成り行きかもしれないとぼんやり感じた。ただの仲のいい友達だったならずっと一緒にいられたのかもしれなかった。ぼくは彼を好きになってしまったことを、そしてその恋にぼくの心が全てを支配され、彼にさえその乱れや揺らぎが及んでしまったことを、悔やみはしないけれど悲しく思った。
・他人の悲しみを知らずに他人を裁くことはできない

結局ぼくは心や感情が乱されながらでも、中学高校で学年トップを6年間維持し続けた。学問も場である「学校」におけるその肯定感は絶大で、ぼくは自分の動かし難い同性愛の絶望的な運命に滅ぼされることなく、高校卒業まで生き延びることができた。学問における揺るぎない肯定がなければ、ぼくは自分の運命がもたらす徹底的な否定の雨を、どのように防ぐことができていたのだろうか。ぼくは自分の運命に絶望しこの世から消滅してしまっていただろうか、それとも人はしぶとくも、また別の肯定の在り処を見出すものだろうか。
周囲からぼくの様子を見れば「ずっと学年トップだった人が大学受験に失敗した」ととらえられるだけに過ぎないだろう。それはきっと意外で面白い話題として周囲に語り継がれることだろう。けれど彼らは何もしらない。仲のいい友達も、頼もしかった先生も、親でさえ、ぼくの心の中に巻き起こっていた嵐の悲しい姿を誰も知らない。人の心の中に宿る寒さや冷たさは、他人には何ひとつ見えない。それなのに人はまるで何もかもが見えているかのように、口を開いては噂することをやめない。
ぼくは初めて人を好きになることを通して、人というものはこんなにも他人の心の風景が見えないものなのだということを学んだ。それは初恋以来ぼくの心の中を常に支配していた嵐や絶望が、他の誰の目にも見えないことを知ったからだった。ぼくの悲しみは、ぼくしか知らない。ぼくは彼を好きになったことを悟られないようにするため、周囲には何事もなかったかのように明るくふるまう。けれど彼を好きになって以来、ぼくが心の中で泣いていない日はなかった。学校では明るく楽しくふるまって、家でも何事もないかのように日常を営んで、唯一たった1人になれるお風呂の中で、毎日声を殺して泣いていた。人の本当の悲しみを、他人は何ひとつ知ることはできない。
誰かが転んだり、失敗したのを見たとき、他人は愚かな不注意だとその人を裁くだろう。そしてその人の不幸を心の中で少し喜び、転んだのが自分でなくてよかったと心慰められるだろう。しかし決して、他人を裁いてはならない。その人の悲しみは、その人にしかわからないのだ。その人の人生や生命には、その人にしか背負えない悲しみや運命が常に宿っていて、そのどうしようもない悲しみが見えやしないのに、人が人を裁くことは傲慢だ。
他人を裁くということは、何ひとつ悲しみを背負わなかった人のすることだ。ぼくは決して他人を裁けない。何ひとつ変わりのないあなたの笑顔の奥には、どんな悲しみが本当は潜んでいるのだろう、どんな運命があなたを苛んでいるのだろう、そんな風に思いやっては憂世を渡るだけ。どんなに普通にふるまっているあなたの心にも、惜しみなく慈しみの思いを注ぎ続けよう。本当は泣いているのなら、本当は嘆いているのなら、そしてその悲しみの根源が、他でもないあなた自身の生命に根ざしているのなら、もはや慈しむより他はない。
あなたの孤独が、ぼくにも聞こえる。背負わされた重き荷は、あなたにしか背負えない運命。決して他人に渡すことはできない、他人には決して見えはしない。ぼくの悲しみは、ぼくだけのものだった。そしてあなたの悲しみは、他でもないあなただけのもの。ぼくはあなたの悲しみを背負えない。あなたもぼくの悲しみを担えない。それでもいいというのならば、どうせひとつにはなれないことを知っていても、心だけでも共に行こう。ぼくはあなたにはなれない。あなたはぼくにはなれない。ぼくとあなたの孤独は、決して交わることのないねじれの位置。けれどぼくがぼくの孤独をひたすらに抱える限り、あなたがあなたの孤独を究極に求める限り、ぼくたちは矛盾するように孤独という名の橋を渡り、いつしかひとつの異郷へとつながる。