どうしようもない孤独を抱える魂たちへ。

思春期の同性愛者(ゲイ)が孤独を感じる7つの理由
目次
・ぼくの初恋は高校2年生で同級生の男の子を好きになった
ぼくの初恋は高校2年生、16歳のときだった。同じクラスの同級生の男の子を好きになって、ぼくは自分が同性愛者だということを知った。
男が男を好きになることの先には、様々な種類の孤独が待ち構えていた。自分では選びとれない運命に翻弄されて、ぼくは孤独の中をさまよい歩くしかなかった。
・ぼくが純粋に人を好きになることで、大切な人たちが悲しんでしまう孤独
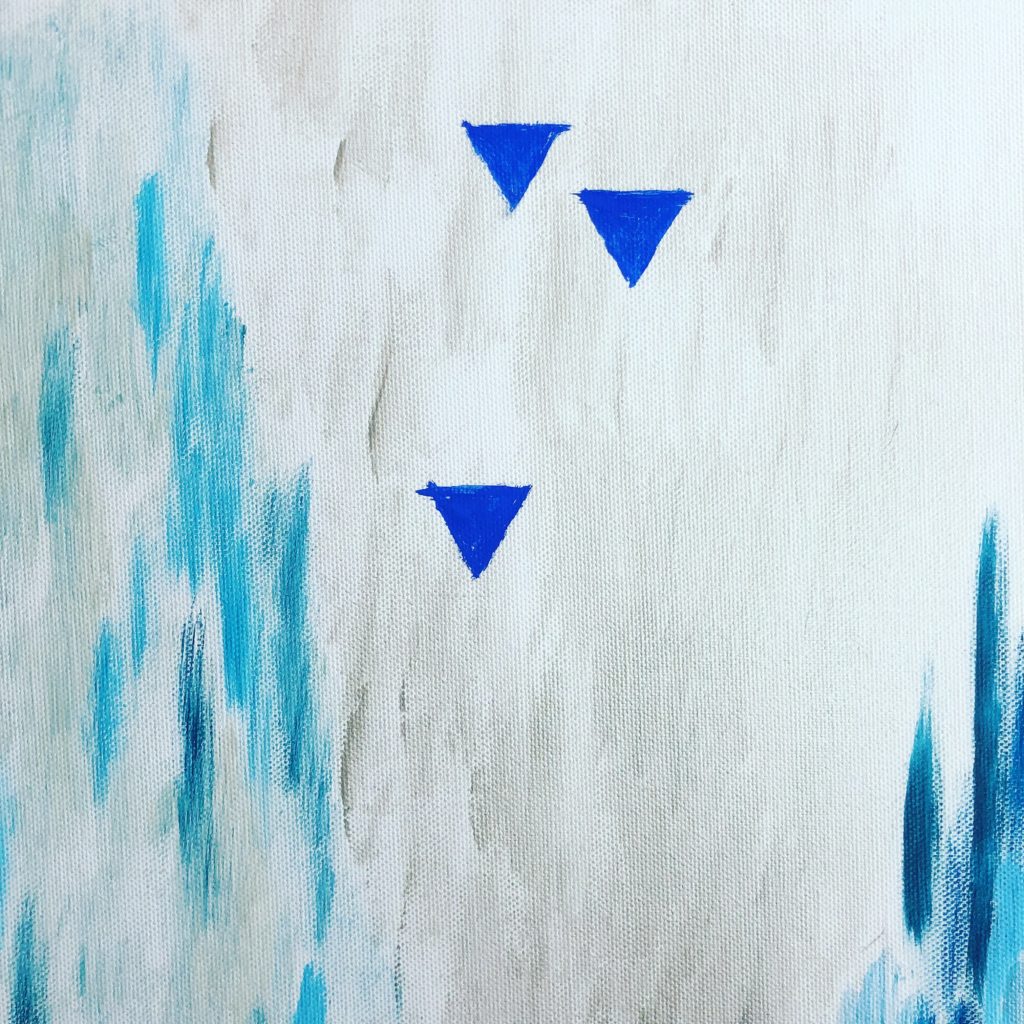
人を好きになることは素晴らしいことだと、ぼくたちは幼い頃から教えられて育った。けれどぼくが人を好きになって感じたことは、自分が罪人であるという意識だった。ぼくが人を好きになればなるほどに、ぼくの大切な人たちが悲しむような気がした。お母さんやお父さん、おばあちゃんやおじいちゃんを失望させるような気がした。気がしただけで本当にそうなのかはわからないけれど、きっとそうだという不思議な確信が心の中にあった。自分が人を好きになればなるほどに大切な人たちを傷つけてしまうという、自分では決めることのできない運命に、引き裂かれるような矛盾を感じた。
ぼくは人を好きになることで、大切な人たちが喜んでくれる人生を歩みたかった。そんな人生が当たり前だと思っていたし、ぼくが純粋に人を好きになることで誰かを悲しませるくらいなら、生きていても仕方がないんじゃないかとさえ思った。これから先もずっと決して祝福されない恋を繰り返しながら生きていくのかもしれないと思うと心を突き刺されたような痛みを感じた。
・男の子を好きになったことを誰にも言えない孤独

ぼくは同級生の男の子を好きになったことを、他の誰にも言えなかった。人に話せば少しは楽になれるのかもしれない悲しみや悩みも、たったひとりで抱え込むしかなかった。みんなの前では何の悲しみも持たないふりをして笑って、夜になったら家のお風呂でいつも泣いていた。心がもうもたなくなっても、その時は自分が壊れるしかないと感じていた。たとえ自分が壊れても、この恋を秘密にしなければならないと自負していた。
好きな人の話を気軽に相談している同級生たちがうらやましかった。ぼくも好きになったのが女の子だったら、いつでも恋を共有して打ち解けられるのにと感じた。秘密の恋が心を占める割合があまりにも大きすぎて、ぼくの心は他の誰からも隔絶され、誰にも言えない恋を持て余していた。普段はみんなと笑って普通に過ごしているのに、心の中は常に孤独で満たされて泣いていた。体の内側では常に涙を流していた。
・「性」の話題で共感できなくても頷かざるを得ない孤独
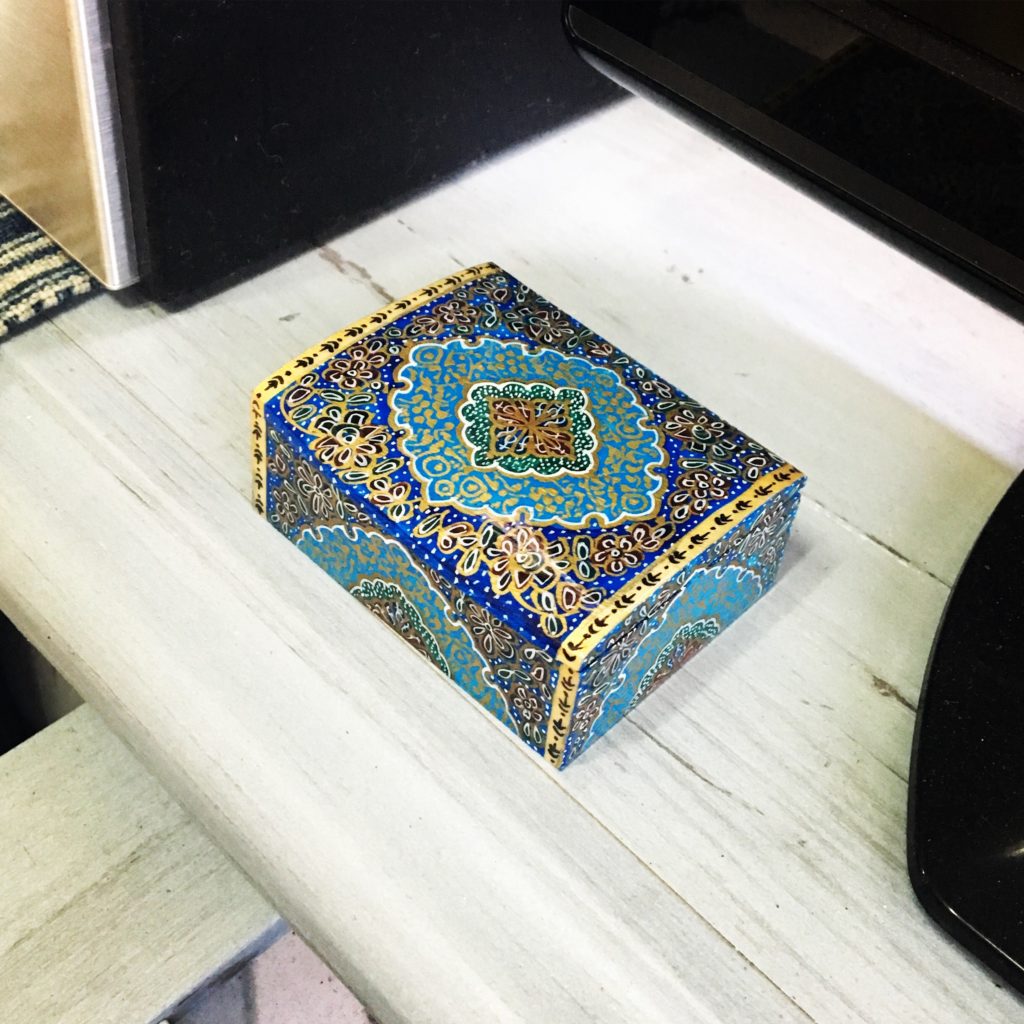
男子高校生の話題といえば、専ら性に関することや女の子のことが多くなる。そんな話題の中に身を置いていると、自分が他の男子とは全く違った感性を持っていることに気づかされる。周りに合わせて頷いていても、本当はほとんど共感できないことばかりだった。「性」という動物として最も基本的で根本的な話題で心から共感できないということは、思っていたよりも孤独感を感じるものだった。逆にこの「性」という話題で本当に共感できるほとんどの人々は、ぼくの孤独感とは裏腹に、最も強い精神的な繋がりや結束力を感じるのだろう。
世間では隠すべきだとされている下ネタや性の話題。しかしそれは初めから暴かれている秘密の話題だ。誰だって同じ肉体構造を持った人間なのだから、誰もが自分と同じように排泄したり生殖行為をするに決まっている。みんな同じなら隠しても端ならバレているので隠す意味もないのだが、そこを敢えて隠して、敢えてわかりきった秘密を暴くことに、人間の交流の”妙”が出現する。なんだやっぱりみんな同じなのだと、動物的なのは自分だけじゃないのだと、当然の安堵を心にもたらすことができる。コミュニケーションの技術としてここに人間たちは根源的な心の繋がりや結束力を見出すが、それを見出すことが難しかったり見出すことに本当は失敗しているのは寂しいことだった。
・嘘をつかなければ生きられないという孤独

ぼくたちは幼い頃から大人から、嘘をついてはいけないと教えられる。けれどぼくは初恋を通して、大切なことでも嘘をつかざるを得ないことがあることを痛いほど実感した。むしろ大切なことほど、嘘をついて自分を取り繕わなければならない運命に絶望した。人を好きになるという純粋で美しい気持ちを覆い隠して、偽りを塗りたくりながら歩いていかなければならない日々なんて予想もしていなかった。だけど嘘をついて生きていかなければ、偽りで自分を満たさなければ、全てが壊れてしまうような気がした。
「嘘をついてはいけない」「嘘をつかないことが誠実な生き方だ」と言い放った大人たちをぼくは浅はかな偽物だと感じた。本当に真剣に傷つきながら人生を生きてきて、そのような意見に果たして行き着くだろうか。そんな正しさはどうしようもない運命を背負った魂たちを傷つけるだけのナイフだと感じた。そんな正しさで身を包んで自分を匿っている浅はかな人間たちを恨んだ。定型文の正しさをふりかざし押し付けるだけの愚かな生き様は、切なる思いで生き抜いているすべての美しい魂たちに対する冒涜だと感じた。もしも幼い頃に「嘘をついてはいけない」と教えられなければ、どうしようもなく嘘をつかざるを得ない運命を背負った者たちも、もっと安からに生きられるかもしれないのに。
・世界から否定の雨を注がれているような孤独

人が人を好きになるという純粋な思いは絶対的に美しいと心から信じられたけれど、男が男を好きになることでそれとは逆の「否定」を常に全身に浴びているような感覚に陥った。自分が否定されるべき存在であること、自分が異常な存在であること、自分が間違った存在であること、自分は幸せにはなれないのだということ、自分はこの世にいてはいけないのだということ、否定が様々な形をとってぼくの心を支配し、誰にも相談できない分ぼくは自分ひとりですべての否定を受け止めながら歩いた。
この否定的感覚はどこから訪れるのだろう。世界の感性がぼくを襲って来ているのかもしれないし、もしかしたら全部自分自身で作り出した自分自身を傷つけるための否定なのかもしれない。けれどそんなことはどうでもいいと思えるほどに、ぼくの心は否定の海に埋もれていった。
・未来の人生に絶望しか見出せない孤独

ぼくはこれからも、人を好きになっても結ばれることはないのだと感じていた。同級生の男の子を好きになっても、自分も男なのだから好きになってもらえるはずもないことははじめから分かり切ってしまっているし、叶わない思いをごまかして生きるしかなかった。それでも無理だとわかっていても、どうしても近づきたくなって、もっとぼくのことを好きになってほしくて、もしかしたらもしかしたらと淡い期待を抱いて、最初からわかっていた結末が訪れて、心がボロボロになっていった。
ぼくはこれからどうなってしまうのだろう。また同じように近くにいる男の人を好きになって、また叶わないことを知って、そうやって一生心を滅ぼされたまま死んでいくのかもしれないとぼんやり予感した。愛した人には、絶対に愛されない運命。どうしようもない定めがぼくの背にのしかかり、動けなくなりそうだった。動物として根源的な性に関して心から共感もできずに、嘘で取り繕いながら生きていくべき虚しい宿命。男を好きな男の人はこんな孤独の中をどうやって生き抜いて行くのだろう。参考になる人を見出すこともできずに、未来は冷たい暗黒に支配されているような気がした。
普通ならば恋愛して、結婚して、子供を作って、育てて、労働して、退職して、老後を過ごしてというような、安定した既定の線路が用意されている。でも男の人を好きになる男の線路は、さがしてみても見当たらなかった。
・どうしようもない運命さえ貫こうと決意する孤独

傷つくだけだからやめておけばいいのに、ぼくは彼に好きになってほしかった。どうせ無駄だとわかりきっているのに、もっと近くにいたいと願ってしまった。恋は理屈は論理ではなく、直感的で野生的なものだと気がついた。
論理的に考えれば傷つくだけだとわかりきっていることなんて、時間と体力の無駄だから避けるに越したことはない。しかし論理を超越した恋の衝動は、ぼくを突き動かして思いを貫かせた。ぼくは傷つかないために生まれて来たんじゃないと感じた。ぼくは死なないために生きているんじゃないと悟った。もしもこの恋で傷ついても、死ぬことになってしまっても、その結末よりも価値のある貫かれる思いが、ぼくの心の中で燃えているのを感じた。どうしようもない運命にもぬぐい去れない孤独にも、立ち向かって行こうと心に決めた。
・ぼくの高校時代の初恋について
・大学時代の2番目の恋について
・同性愛について










