言葉にしたら消えてしまう儚い春のような日々が、この世にはある。

ノンケの彼とゲイのぼくは、どんなに好きだと抱きしめ合っても恋人同士にはなれなかった
目次
・大学時代、ぼくは好きなノンケと「好き」と言って抱きしめ合った

大学時代、ぼくは同級生の男の子のSに片思いをしていた。ぼくが好きな気持ちを我慢できずに彼に告白すると、彼もまたぼくのことを「好き」だと言って会うたびに抱きしめれくれるようになった。彼が男の肉体を愛さないことは明白だった。彼の部屋には女性の肉体が露わになったDVDがいくつも並べられていたし、携帯の中を見ても女性の裸体で埋め尽くされていた。他のほとんどの男の子がそうであるように、彼が女性の肉体に発情し女性の肉体を必死になって必然的に追い求めるように創られていることは明らかだった。
それなのにぼくと会うたびに、彼はぼくに「大好き」だと告げてくれた。ぼくと彼は「大好き」と言い合って、強く抱きしめ合った。毎日彼の部屋のベッドで一緒に眠るようになり、2人ともまだ誰にも触られたことのない青い果実を、お互いに衣の上から刺激し合って遊んだ。ぼくの果実を彼しか触れたことがなかったし、彼の果実をぼくしか触れたことがなかった。ただ手のひらと果実の間に衣をひとつ隔てていたことが、春の中にいるぼくたちの尊い未熟さだった。ひとつの衣が取り払われてぼくたちの青い液体が大地を潤せば、もう二度と春はやって来ないような気がした。
・ノンケの彼とゲイのぼくは、どんなに好きだと言い合っても恋人同士になれなかった

大学生になると友達のうちの様々な男女が結ばれていた。試験と実習が幾度となる繰り返される多忙な医学生の学生生活の中で、友達同士の恋愛話を聞くことは適度な気分転換になっていた。仲の良い友達同士で集まる飲み会で新しく恋人同士になった男女に向かって、みんながどんな風に告白したのか質問した。彼らは「普通に好きだよって言って告白したよ」と答えた。ぼくはその話を聞いて、とても不思議な気分になった。好きだよと言い合うだけで、そんなことだけで恋人同士になれるなんて羨ましいと感じた。
ぼくとSだって会うたびに何度も「大好き」という言葉を交わしていた。そして普通は恋人同士でしかやらないようなそれ以上のこともたくさん経験していた。それなのにぼくたちは決して「恋人同士」ではなかった。2人のことを「恋人」と名付けてしまえば全てが壊れてしまうような、彼のことを「彼氏」だと言ってしまえば全てが終わってしまうような、不思議なことに誰から教えられることもなく、2人の秘密を明確な言葉として表現することは禁じられているのだと感じずにはいられなかった。
人は言葉にしなければ不安だから、なんでも名前を付けたがる。「恋人」とか「彼氏」とか「彼女」とか「結婚」とか「夫婦」とか「夫」とか「妻」とか、名前を付けることで言葉がなかった時には曖昧だった人間関係が確定され、安心して固定化された名前や制度の元で胸を張って生きることができる。もしも時の流れと共に関係性がわからなくなったり壊れそうになった時には、その名前にすがりついて安らぎを得ることができる。名前とは、人間にとって心が迷った時に帰り着ける巣のようなものだった。
だけど本当に人間関係に名前なんてあるのだろうか。本当は名前なんてないのに、移りゆく人間関係が不安で、心を安心させるために無理矢理に人間関係を言葉で冷凍保存させようとしたものが、人間関係の名前なんじゃないだろうか。ぼくとSの関係には、名前がなかった。ぼくはそれを寂しいと思った。名前がなければ、約束がなければ、誓いがなければ、いつだって2人の関係は崩壊するかもしれない危うさを内包していた。名前にすがりついて、彼との春の季節を美術館のガラスの箱の中のように閉じ込めることはできなかった。
けれどぼくとSの関係に名前がないことを、尊く誇らしくも思った。いつだって消えてしまうかもしれない春だから、ぼくたちは2人でどこまでも慈しんだ。儚く今にも失ってしまいそうな淡い光が、ぼくたちの裸体を包み込んで眠らせた。終わらない春はないのだという喪失の予感が、ぼくたちをより強く抱きしめ合うことを促した。もしも次に春が訪れることがあったとしても、同じ果実の熱さと潤いは二度と戻らないのだと悟った。
・男性が女性の肉体を求めるというありふれた当たり前の現象

ある日彼は女の子の話をぼくに聞かせた。気になる可愛い女の子に彼氏がいて落ち込んでいるという話だった。ぼくと「好きだ」と言葉を交わすようになってから女の子の話をすることがなかったのに、やっぱり彼は今でも女の子の肉体を求めていた。
それは分かり切った自然の摂理だった。他の男の子がそうであるのと同様に、Sにも女性の肉体を強く求めるような本能が遺伝子の底に埋め込まれていた。水が高いところから低いところへ流れるように、空気が重いところから軽いところへ流れるように、まさにそのようなごく自然な成り行きで、Sという男性の肉体は女性の肉体へと激しく流れ込むように創られていた。それは必然的な本能の創造であり、変えることのできない神様の命令だった。男が女の肉体を獣のように求めることで、新しい生命は誕生した。ほとんどの男性は女性の肉体を貪るように設計され、その結果として人類の子孫は絶えることがなかった。Sはその中のありふれたひとつに過ぎなかった。
Sが女の子の肉体を求めることは当たり前だ。不思議なことは、彼がぼくに「大好き」だと言ってぼくの肉体を抱きしめてくれることだった。ぼくの肉体を抱きしめる時、彼の果実はいつも熱く膨張し鼓動していた。彼は愛するはずのない肉体を抱きしめていた。彼は触るはずのないものを慈しんで握りしめた。ぼくもまた、触られるはずのない手で彼の果実の野生を感じ取った。彼が女性に「好き」だと告げるのは当たり前だった。彼が女性の肉体を抱きしめることも当然だった。それなのに彼がぼくの全てを求めてくれることを、ぼくは尊い超越だと感じた。彼がぼくを求めてくれることは、ひとつも当たり前じゃなかった。
・ぼくは意味のない「好き」という言葉を宝物のように抱きしめて眠った
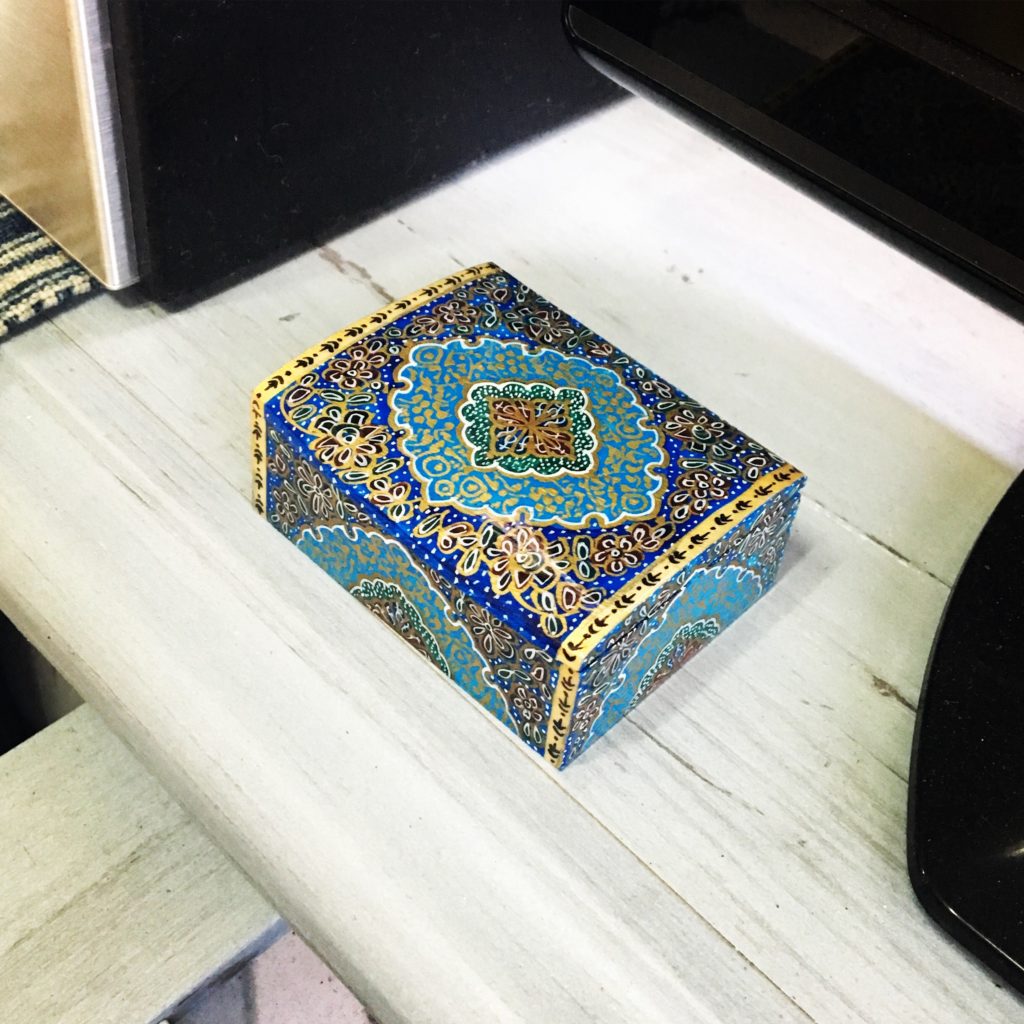
Sの中ではぼくに「好きだ」と言って抱きしめ合うことと、別のところで女の子の肉体を探し求めることは矛盾せずに両立しているようだった。ぼくに気になる女の子の話をすることも、当然許されるものと信じているらしかった。ぼくたちは「恋人同士」じゃない、言葉として固定された関係ではない、そのことを利用して彼は矛盾の中を何食わぬ顔で泳いでた。
ぼくが悲しみに暮れることを、彼はきっと知っていただろう。いつもぼくに告げてくれる「大好き」という言葉を、他の人にも言うことを許されているはずだとふるまうSの態度が悔しかった。「好きだ」という言葉を、この世界のたったひとりにしか言ってはならないという決まりはないけれど、それでもぼくはSのたったひとりになりたいと祈っていた。Sはぼくの気持ちを知っているのに、敢えてぼくの心を切り裂くことで正常な世界へと戻ろうとしているのかもしれなかった。「好きだ」と言い合ったなら他の人には言わないでほしいという、人として当たり前の願いさえぼくには手の届かない贅沢品だった。
Sはいつかぼくではない女性の肉体に「好きだ」と告げるだろう。そんな言葉に価値なんてあるのだろうか。そんな言葉を宝物のように慈しんでいた自分が虚しく感じられた。気になる女の子の話をした後でさえSはぼくに「大好き」と言いながら、ぼくの果実をいつもより優しくいじってくる。
ぼくは悲しくなって彼に告げた。「大好きっていうのは本当に大好きじゃないと使ったらあかんねんで。」すると彼はすぐにぼくの顔を見て「ふーん、じゃあ大好き」と呟いた。
・大学時代の2番目の恋について
・ぼくの高校時代の初恋について
・同性愛について












